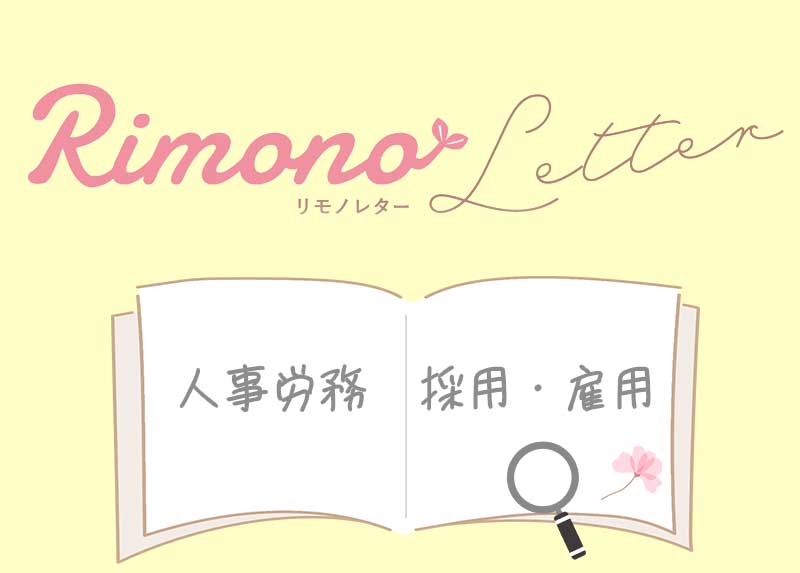前号のリモノレターでは中途採用者の早期離職や問題行動などについての事例を分析し、正確な採用情報の明示、適性診断の活用、前職調査の実施などの取り組みが重要であることをお伝えいたしました。こうした採用選考を経て見極められた中途採用者がいよいよ入社する際、本人がなるべく早く仕事や職場に馴染み成果を上げることができるよう工夫しなければなりません。
リモノレター「中途採用を工夫する」2025.1.21
https://rimono.co.jp/2025/01/21/rimono_letter202501/
本号では、中途採用者の受入れ支援(オンボーディング)について業務・組織・規律の3つの要素から考えていきます。たとえ採用選考を精緻に練ったとしても入社後の受け入れが現場任せである場合、現場が求める人材像とは乖離している、責任者が外出・出張で不在である、繁忙期の最中で手が回らないなどの理由で受け入れ支援にバラつきが生まれる可能性があります。
会社が採用活動を工夫し十分な資質を持つ人材を採用できたとして、中途採用者が入社前の期待と入社後の現実に隔たりを感じるのは当然のことです。前職の経験があっても、仕事が過酷であったり逆に拍子抜けであったりなどでモチベーションが低下することもあれば、外部からは想像できなかった企業風土による独自ルールに当惑することもあります。
本人も支援を乞うことに遠慮がある一方で、周囲の社員も即戦力として期待するあまり過大評価する、様子見のまま放置する、あるいは簡易な支援で切り上げてしまうケースが多いかもしれません。転職サービス会社などの調査によれば、入社後の中途採用者がショックを受ける現実として「企業風土」、「人間関係」、「過重労働」などが上位に挙げられています。
企業風土や人間関係については本人と周囲の化学反応で左右される側面があるため、どちらか一方の問題ではないと言えます。しかし中途採用者は前職までの経歴や思考・行動の枠組みが多様であり、見知らぬ環境で人間関係を築かなければならない点にハンディキャップを抱えています。意思疎通の技術によって一定の範囲は解消できますが、信頼関係を築き上げて仕事の成果を上げるまでには時間を要するのではないでしょうか。
【お伝えしたい内容】
1. 業務適応
中途採用者の実務経験や基礎能力によって入社後の業務適応における支援の進め方が異なります。パート・アルバイトから正社員に転換した場合は、周囲の社員がその働きぶりや人間性を把握できており本人も職場の人間関係を理解しているため、担当業務や責任範囲の変化した部分に当て込む個別の適応支援を実施することで十分かもしれません。
中途採用者が外部から入社した場合、上長は本人の経歴や適性診断の結果を参照しオリエンテーション(入社日面談)を実施することなどで、おおよそ本人の働きぶりを推測できます。十分な経験・能力を持ち管理職や専門職に採用された人材である場合は、部門横断的な業務インフラを折に触れてOJT形式で説明することで、必要十分な適応支援となるはずです。
【業務インフラ】
- 業務報告 ……
- 会議体、報告書、PDCAサイクル、日程管理、ファイル管理
- 勤怠管理 ……
- 残業申請、休暇申請、緊急連絡、安否確認
- 決裁権限 ……
- 取引契約、見積、経費、ワークフロー
- システム ……
- 基幹システム、業務アプリ、クラウドサービス
- 備品設備 ……
- PC・携帯端末、複合機、社用車、セキュリティ、エアコン
- 環境管理 ……
- 身だしなみ、職場の清掃、トイレ・洗面、飲食
- イベント ……
- 朝礼、外出・出張、セミナー、交流会
他方で一般職層に採用された中途採用者の経験・能力が未だ十分なレベルでない場合は、試用期間を目処に経験豊富な先輩を指導員として付ける、個人日報を作成させて上長や指導員が確認・指導する、社内インフラの習得や人間関係の構築について面倒見が良い同僚をサブ指導員として付けることなどが効果的な適応支援になります。
【アンラーニング】
キャリアの自律性を意識し実務経験を積んだ中途採用者は、自分なりに成果を上げてきたことに自負を持つ傾向がある点に留意しておきます。採用選考の過程で企業風土を理解し受け入れる覚悟を持っていても、現実問題として当惑を覚えたまま業務に当たることがあるはずです。上長や周囲から「それは違う」と指摘を受ければ、これまでの経験を否定されたように感じストレスを抱えてしまいます。
そうした時は「アンラーニング」の考え方を知ってもらうと良いかもしれません。「アンラーニング」とは、実務経験による知識やスキルのうち陳腐化したものを捨て、新たなものを学習することを指します。従来から馴染んだ仕事の進め方であっても柔軟に取捨選択し、本人だけではなく周囲の社員も含めて双方向で「アンラーニング」を織り込んで仕事に取組むことが望ましいでしょう。
2. 組織適応
中途採用者のオリエンテーション(入社日面談)においては、採用選考の過程で会社から本人に伝えた経営理念や事業方針などの基本的な情報に加え、配属先の上長から担当業務についての具体的な内容、仕事のやり甲斐や成長の可能性などを伝えることが一般的です。仮に本人が抱いている期待が現実的ではない場合、仕事の厳しい面を含めて率直な情報を伝えることで理解を深めてもらいます。
入社した直後は業務適応と組織適応を並行して支援する時期です。中途採用者の組織適応とは、自分への役割期待を踏まえて上長や同僚との関係性を構築することと言えます。この期間に経営トップから本人に対する期待と励ましの気持ちを伝える、これから一緒に働く先輩や同僚が参加するグループ面談で顔合わせを行うなどで、本人が職場の雰囲気になじもうとする背中を押すことになります。
組織適応については、中途採用者が変化を持ち込む存在であるとの心構えを職場の上長や同僚が持たなくてはなりません。中途採用者の新しい視点での言動を受け止めたうえで、現状の業務プロセスや意思決定の背景にある価値観を自分なりの言葉で伝える準備をしなければならないはずです。一方的に否定することや言わなくてもわかるだろうと押し付けるだけでは、双方の期待と現実が見合うことは難しくなります。
前述の通り中途採用者が様々な実務経験や基礎能力を持つために、業務適応の支援は個別性が高く組織適応とのバランスの取り方も異なります。試用期間内を目処に(あるいはその後も継続して)上長による面談を定期的に実施し、直近の業務報告を題材に意見を述べ合い、中途採用者に「これならやっていけそうだ」という安心感を与えることが有効な場合もあります。
面談に際して上長が中途採用者に意見を求める場合、互いの役割や責任を認識しつつ「自分はこう思うが、あなたはどうか」と具体的な考えを示して対話する、興味関心によって社内の関係部門を紹介することで人間関係を広げるなどの方法もあります。上長がコミュニケーション技術に頼った表面的な対話を行うだけでは、信頼関係が生まれず中途採用者の組織適応が進まないことに注意する必要があります。
参考資料: 労政時報「定着・早期活躍を支える新卒・中途入社者の組織適応支援の勘所」2020.04.10
https://www.rosei.jp/readers/article/77849
3. コンプライアンス
業務適応や組織適応を優先することで後回しにしてはならないのは、中途採用者に対するコンプライアンスの確認・指導です。コンプライアンスは、基本的には企業が国内外の法令・諸制度や社会の倫理規範に適合した企業活動を行うことを指しますが、経営者や従業員の業務上および個人的な活動においても規律遵守が求められることはご承知のとおりです。
経営者や従業員が何らかのかたちで違法行為や不正行為を行えば、個人のみならず企業の信頼も低下してしまいます。取引停止や顧客離れが発生する、あるいは多額の損害賠償を請求されるなどで経営を揺るがすことがあります。近年では顧客個人情報などの漏えい事件、ハラスメント行為、助成金の不正受給などが問題になっています。
コンプライアンス推進の取り組みについて、大企業では会社法によって内部統制システムの構築が義務化されていますが、中小企業においてもコンプライアンス方針の宣言、行動規範やマニュアルの策定、研修教育の実施、相談通報窓口の設置などが適切とされています。しかしながら、身元保証書や機密保持誓約書を取り交わす、就業規則に記載された服務規律を説明するなどに限られているのが実態かもしれません。
また、前職で営業秘密として管理されていた会社の顧客情報や技術情報を中途採用者が保持している場合、そうした情報を不用意に利用することで不正競争防止法違反にならないよう注意が必要です。とくに中途採用者がライバル企業から転職している場合、営業秘密の取り扱いについてはコンプライアンス上のリスクも高くなります。
最近発生した違反行為の事例を踏まえて注視しておきたい点はソーシャルメディアの適正利用です。Facebook、Instagram、X(エックス)等のSNSで従業員は業務遂行上知り得た個人情報などを発信・開示してはならないはずですが、万が一にも会社が違反行為を発見した際は従業員に情報の削除・訂正を求める必要があります。思わぬ油断で営業情報や顧客情報などの漏えいが発生しないよう、折に触れて注意喚起をしておくことも大切です。