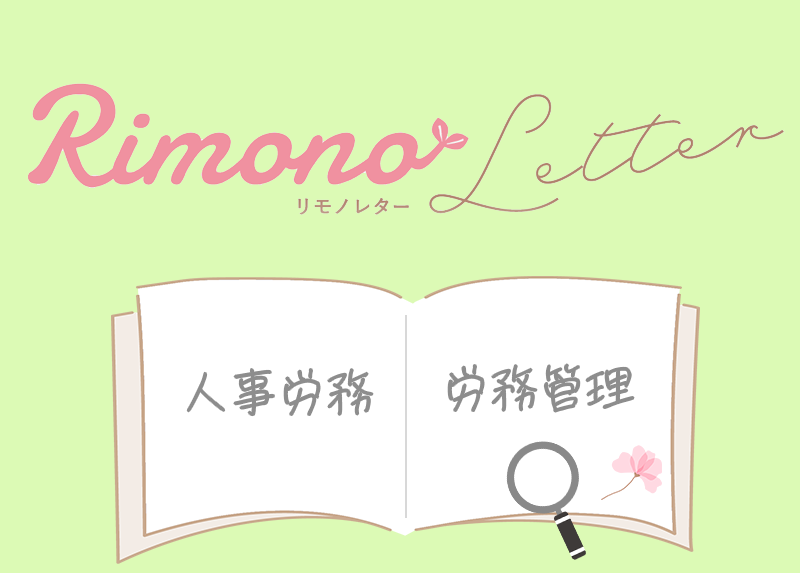企業活動に影響を与える自然災害等の発生に際して、会社は被災情報の把握、緊急措置の発動、代替拠点の切替え稼働などを行う体制が整備されていない場合であっても、従業員の安全を確保しつつ危機対応の情報収集・指揮系統を集約させて、可能な限り迅速に通常営業を復旧させようとしなければなりません。
ここで言う自然災害等は、地震、台風、豪雨、大雪などの自然災害のみならず、火災や停電・断水などの事故災害、道路や鉄道など交通網の混乱、ネットワークやシステムの障害、海外拠点での政治・軍事的な騒乱、大規模なテロ事件、感染症の流行などのあらゆる非常事態が想定されます。
自然災害等の対応において会社が従業員の安全を確保することは、安全配慮義務を定めた法令を根拠とするまでもなく最優先です。しかし、混乱する現場の被害情報を把握し緊急措置を発動すること、あるいは被害が甚大な場合には実施可能な措置の優先順位を付けることも必要になります。
〈労働契約法 第5条〉
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
緊急措置の発動にあたっては、従業員の安全確保を図ったうえで様々な企業活動への影響を見極めなければなりませんが、たとえ自社へ直接被害がなかったとしても、いわゆるサプライチェーン(調達→生産→流通→販売までの一連の流れ)の中断、ネットワークやシステムの障害により思わぬ事態が発生することがあります。
ご既承の通り、企業の危機対応については「BCP(事業継続計画)」の策定が肝要ですが、BCPの策定と防災体制の構築・整備を一旦区別して考えること、災害の種類を問わず被災後に想定される損害の内容・程度に合わせて手順方法を策定すること(オールハザード型)で、比較的取り組みやすくなると思います。
本号では、自然災害等の危機対応について防災体制の構築、BCP(事業継続計画)の策定、および点検訓練の実施という枠組みで要点をまとめました。
内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査 (概要)」(令和6年3月)
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/chosa_240529.pdf
【お伝えしたい内容】
1. 防災体制の構築
防災体制の構築のためにまず取り組むべきことは、事業拠点を置く地盤地図(ハザードマップ)の確認、建屋・建造物の耐震補強、防火・消火設備の点検、機械装置の非常停止装置の整備、高架棚の転倒落下の防止、非常用電源の増設など、必要な費用を投じて事業基盤を強化することであると思います。
次に、従業員や外部来訪者の避難経路の決定、避難誘導や安否確認の方法手順の決定(電話番号・メール・SNSなど複数の連絡先を把握すること)、ヘルメット・ライト・飲料水・食料品・毛布などの防災グッズの備蓄、被災者の救急医薬品・衛生用品や携帯トイレの備付など、安全確保に取り組む流れになります。
また、災害発生直後の出社・帰宅や事業所内での待機などの指示を下す役割を、管理部門に統括しておくことが必要です。管理部門は経営トップと協議しつつ、地震津波速報・気象警報・交通情報などに客観的な判断基準を求め、個々の従業員の通勤距離や家庭環境などの事情を考慮して指示しなければならないはずです。
従業員の海外出張先で政治・軍事的な騒乱や大規模なテロ事件などが発生した場合には、情報が混乱して安否の確認が困難になります。現地事情に詳しい日系企業の拠点や邦人保護に当たる日本領事館の支援を求めるなど、社内体制にもとづく対応では追いつかなくなる可能性も考えられます。
システム障害については、必要なソフトウェアをネットワークで利用できるサービス(SaaS)が普及したことで直接の心配はなくなりました。とはいえウィルス対策ソフトや端末ごとの不審な挙動を検知するシステム(EDR)の導入など、サイバー攻撃への対策を確実に実施しておくことが大切です。
2. BCP(事業継続計画)の策定
BCPとは、企業が自然災害等の発生による影響を最小限に抑え、事業継続あるいは事業中断からの早期復旧を図るための手順方法をあらかじめ計画しておくことを意味します。BCPの策定は、東日本大震災で被災した企業が事業中断に追い込まれて倒産や廃業が相次いだことを契機に拡がりました。
計画策定の基本的な流れは、以下の順序で行われます。
② そのための経営資源を洗い出す。
③ 災害発生による損害を想定する。
④ サプライチェーンの中断による影響を見積もる。
⑤ 目標復旧時間を設定する。
⑥ 復旧のための組織体制や方法手順を決定する。
⑦ 策定計画の全容を資料化する。
前述の通り、BCPは自然災害だけでなく事故災害、交通網の混乱、システム障害、感染症の流行など、あらゆる危機対応を想定し策定されなければなりません。とくに中小企業の限られた人的リソースで計画策定に取り組む場合、BCPは災害の事象ごとの対応ではなく、被災で発生する損害の内容や程度を想定して手順方法を策定すること(オールハザード型)が推奨されています。
BCPの策定については、自治体や関連機関による助言支援を受けられるほか、専門性を持つコンサルティングを依頼する方法もあります。まずは東京商工会議所から公表されている策定ガイドに即し大まかな計画を仮作成したうえで、外部機関と相談するのが現実的といえます。
東京商工会議所「中小企業向けオールハザード型BCP策定ガイド」(令和6年3月)
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1202192
昨年の能登半島地震では、工場火災などの二次災害を防止すること、避難場所やライフラインを被災者に開放すること、BCPの発動によって事業活動を復旧し地域経済を支えることなど、企業が金融・物流・建設を筆頭に幅広い業種で地域の頼れる存在になり得る点を再認識させられました。
*介護サービス事業者のBCP*
令和6年4月より、感染症や災害が発生した場合であっても介護サービスの利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築できるよう、事業者にBCPの策定が義務付けられています。
厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の概要」感染症や災害への対応力強化 令和3年4月
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf
3. 教育・訓練の実施
BCPを策定した後、いざというときに役立てられるよう定期的にBCPにもとづく教育・訓練を実施するサイクルが必須です。仮想被害のもとでBCPの訓練を行ってこそ明らかになる実態が数多くあるため、BCPの内容を教育したうえで机上演習や実動訓練を実施することは欠かせません。
訓練の実施によって役割分担や内容手順を充分に理解できていない事業所・職場を洗い出し、危機対応の混乱を防ぐことができます。一方で、安否確認や緊急集合の訓練を実施した場合に些細な不備で計画通り進行しない場合などは、BCPの実効性を確認・改善しなければなりません。そのためにBCPのPDCAサイクルを平常時に回すことをBCM(事業継続マネジメント)と呼びます。
管理部門は、従業員の生活安定のために給与を支給すること(被災状況によって通常の給与計算や支払手段が適用できない場合もある)、事業停止にあたって従業員に休業を命令すること、BCPの遂行を担う従業員の労働条件を整備することなど、中核的な役割を求められます。
自然災害等の影響で事業停止となった際の給与や休業手当の取り扱いについて、労基法では「使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払い義務はない」としていますが、現実的には給与の全額支給、休業手当相当額の支給、年間休日の就業日への振り替えといった対応が行われています。
参考資料: 労政時報「本誌特別調査 企業の災害対応に関する実態調査」2019.08.09
https://www.rosei.jp/readers/article/76533
これに対して、経営職層の役割は、復旧までの資金繰りを念頭に、大規模災害に際しての公的支援による補助金・特別貸付・信用保証など直近のセーフティネットを踏まえて財務リスクに備えておくことも必要です。あるいはパートナーシップを重視して事業拠点を置く地域における防災の取り組みに参画することで、BCPの拡大版を検討することも考えられます。
中小企業庁 令和6年能登半島災害(地震、大雨)に関する「中小企業者等向け支援策ガイドブック」令和7年1月
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/guidebook.pdf