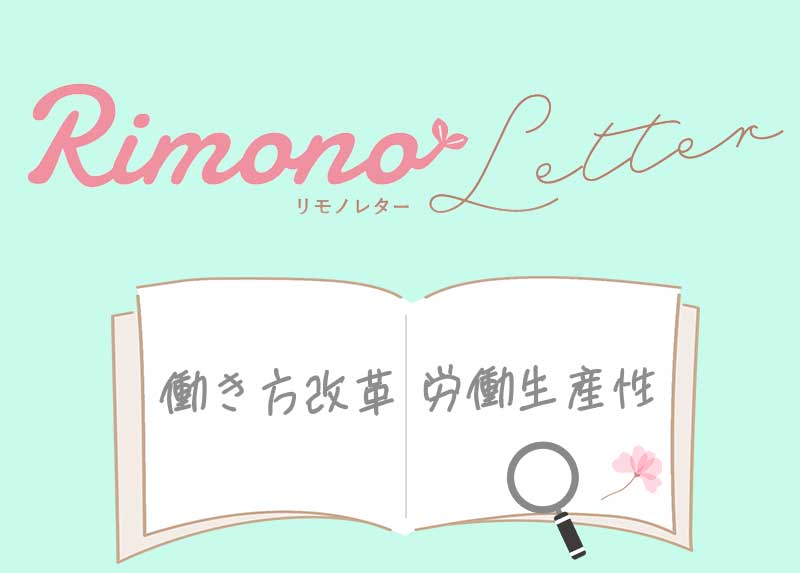出社回帰とは、コロナ禍に広く導入されたテレワークから出社勤務へと戻る動きを指します。2020年以降、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため対人接触を回避できるITインフラが様々な企業で整備されました。これにより、現場部門以外の管理部門や営業部門などにおいて、就業規則に基づく配転命令を根拠とする在宅勤務等オフィス外での勤務形態(以下、「テレワーク」と総称します。)が導入されました。
しかしながら、個人単位のテレワークでは業務の進捗状況が把握しづらく、コミュニケーションや信頼関係が希薄化するといった課題が明らかになってきました。出社勤務によって職場内の連携協力、対面での会議や打ち合せ、朝礼による重要事項の伝達、ランチタイムの雑談などが可能になることで業務遂行の基盤が形成されていたという利点を再認識したものと思います。
一部では、会社の主導ではなく社員の自主性によって出社勤務が増加しているという傾向が見られます。積極的な社員であれば、社内外の関係者を直接巻き込むことでより密度の高い働き方による成果を出したいと考えているのではないでしょうか。業務の特性によっては、個人単位のテレワークとオンラインでの情報伝達の繰り返しよりもリアルな連携から新たな競争力が生まれる可能性があります。
他方で、少子高齢化に伴う構造的人手不足の中、企業は個人の環境・状況に応じて時間や場所を最適化する働き方を提供できなければ人材確保が難しくなっているのが現状です。今後ともITインフラの整備とともにテレワークに対応できる業務プロセスの構築に取り組むことで、コロナ禍以前の働き方に完全に後戻りすることはないだろうと考えられます。
総務省「テレワークの普及状況及び普及・定着に向けた取組方針」2024年6月28日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000957479.pdf
出社回帰にあたりいま一度見直したいのは、労働時間の使い方と業務の効率性です。長期間のテレワークから復帰する場合や入社当初からのテレワークを出社勤務に変更する場合、出社回帰した社員とテレワークを行わずに出社勤務を続けていた社員が、同じ場所に共存することになります。個人単位のテレワークとは異なる職場で仕事の流れを意識しつつ、時間単位での業務効率に注意を払うことが大切です。
【お伝えしたい内容】
1. 会議・打ち合せ
出社回帰によって社内外の会議や打ち合せが対面で行われるようになり、その頻度や時間が増えることは自然な流れと言えます。オンラインでの業務経験を経て、対面での会議や打ち合せでは必要以上に構えることなく意思疎通ができ、双方向の情報交換の密度が高まります。社内の相手であれば、事前に日時を調整しなくてもその場で会議を始められる機動性もあります。
始業時の職場朝礼は短時間の会議体でありながら、各人の仕事への意識を整え、業務遂行に当たって情報共有を図る場として有効です。当日の業務予定を確認すること、緊急性の高い報告を求めること、周知徹底が必要な資料を配付することなどで職場内の透明性が確保されるとともに、業務効率の向上やリスク管理にもつながります。
ただし、会議には「出席人数×時間数×人件費」というコストが発生するだけでなく、開催日時の調整(定例会議を除く)、議題の検討、資料や議事録の作成・配付など、事前・事後の業務に多くの時間と労力が費やされることを再認識する必要があります。また、前例の踏襲により議案内容の確認や調整から会議が始まるといった非効率な流れに陥るケースも考えられます。
関係部門や担当者間で前提知識にバラつきがあったり、同じ内容を複数人が繰り返し質問したり、曖昧な記憶や認識の齟齬が生じたりすることで本来の議題に割かれるべき時間が浪費されるのはもったいないことです。加えて、形式主義にこだわった会議運営や過剰に時間をかけた配付資料や議事録の作成といった、旧来のやり方が復活する可能性にも注意が必要です。
オンラインの会議を重ねたことで習得した資料の事前配布、画面共有、リアルタイムでの議事録作成、30分単位の時間管理などの効率的なルーティンは、対面の会議においても引き続き実践したいポイントです。また、テレワークで利用が急増したビジネスチャットの活用により、非同期型であっても迅速かつ横断的な意思疎通が可能になりました。業務効率の向上に直結するデジタルツールの活用は、今後も欠かせない要素となっています。
2. 通勤・移動・待機
テレワークには、個々の事情に応じて「仕事」と「生活(寝食、育児・介護、趣味、自己研鑽など)」とのバランスを調整できる利点があります。(自発的に仕事以外の有意義かつ健康維持を心掛けた時間を確保できている社員もいれば、公私の切り替えが曖昧になりストレスを抱えている社員もいるなど、様々な実態が想像される側面もあるのですが。)
また、テレワークの大半を占める在宅勤務では「仕事」と「生活」の中間にある通勤時間を削減できるため、通勤負担という生産性へのマイナス要素を取り除けるメリットがあります。とくに都市部では交通混雑や渋滞遅延による疲労や焦燥感が強く、自宅と職場を往復する社員の心身に与えられる影響負担は軽視できません。
こうした知見を踏まえ、毎朝9時に全員出社といった一律の形で出社回帰を実施するのではなく、業務内容に応じて対象部門や社員を限定する、週に数日の出社勤務を命じて他の日にはテレワークを行う、フレックスタイムや時差出勤を導入する、サテライト型のオフィスを設置するなど、多様な選択肢が柔軟に取り入れられている場合が多いようです。
週に数日の出社やサテライトオフィスへの通勤は、通常は労働時間に含まれないと考えられていますが、テレワーク中に緊急会議に呼び出す、業務上の理由で取引先を訪問させる、情報通信機器を活用したモバイル勤務を求めるなど、会社の指揮命令下での移動は、自由な時間活用ができないことから労働時間に当たると見なされる場合があります。
外出や出張での移動時間以外についても、例えば上長への報告のためだけに取引先から帰社させる、間隔が空いた業務のために必要以上の人数を待機させる、配付資料を読み上げるだけの会議に参加させるなど、集団行動による安心感や満足感によって、かえって業務効率を低下させてしまうことは避けなければなりません。
総務省統計局 テレワークによる生活時間の変化 令和4年10月24日
https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/188.pdf
3. ワークスペース(仕事環境)
出社回帰により、社員のワークスペース(仕事環境)に対する期待や要求が変化していることに気付くことがあります。例えば、管理部門の居室ではキャビネットが乱立して空調の流れを妨げている、窮屈な座席配置の間に書類が積み上がっている、床を這う電源・通信ケーブルにホコリがたまる、周囲の会話や電話が騒がしいなど、旧態依然とした状況が残されてはいないでしょうか。
テレワーク中に社員が個人単位で選択・整備できた仕事環境と比較すると、雑然としたオフィスでは自分の仕事に集中しづらく、ストレスを感じやすくなります。また、上長や同僚の顔が見えているのに打ち合せを行う場所がない、複合機の印刷トラブルに手を貸さなければならない、使いたい備品や消耗品の保管場所がわからないなど、出社回帰によってあらためて気付く不便さもあります。
こうした課題に対応するために、出社率の変動に合わせて座席数を調整する、座席配置にゆとりを持たせる、ペーパーレス化と同時に、機能性の高い共用キャビネットを設置するなど、既存の什器や備品を有効利用することでワークスペースを改善することができます。こうして空いたスペースに、島型の座席配置に打ち合せ用のチェアを追加するだけでも円滑なコミュニケーションにつながります。
一定の設備投資が可能である場合は、社員が業務内容に応じて場所を選べるような環境整備が効果的です。集中作業や打ち合せに使えるカウンター、オンライン会議を行える個室ブース、自由な雰囲気で議論できる座席配置の会議室、食事や休憩・気分転換ができるラウンジなど、業務効率とモチベーションを高める目的で設計された様々な設備が市販されています。
出社回帰後は、ただデスクトップに向かって仕事をするのではなく、「作業に集中したい」、「電話をかけたい」、「打ち合せをしたい」といった目的ごとに機動性・柔軟性を可能にする、より良いワークスペースを用意することが望まれます。そのために社員の意見を積極的に聴取すること、運用ルールを明確にすること、利用状況や効果の検証・改善を行うことが重要になります。