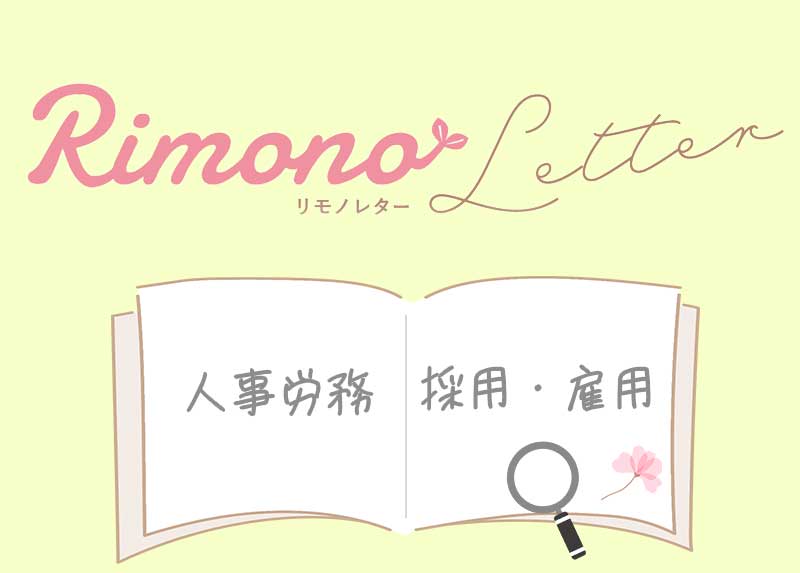会社の事業を維持し安定的に運営する、あるいは発展・拡充させていくための働き手の確保が困難な状況が続いています。ここで云う働き手とは、事業活動の最前線で欠かせない労働力を担う「人手」だけでなく、事業活動の中核を担う力量を備えた「人材」も含まれます。この背景には少子高齢化による就業人口の減少などがあることは既知のとおりです。
東京商工リサーチの調査によると、2024年4月から2025年3月までの期間に発生した企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、人手不足に起因する倒産は、前年度の1.6倍に急増したと報告されています。
TSRデータインサイト
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201258_1527.html
過去のリモノレターでは、フルタイム正社員に拘らず、多様な人材が柔軟な働き方を選べる組織体制や業務運営を通して、働き手不足に対応する取組みを取り上げました。本号では、働き手の合理的な配置、計画的な育成、採用基準の明確化を目的とした「スキルマップ」の導入についてご紹介します。
リモノレター 2024年2月号「働き手を見つける、つながる」 2024/03/04
https://rimono.co.jp/2024/03/04/rimono_letter202402/
リモノレター 2024年10月号「働き手を組み合わせる」 2024/10/16
https://rimono.co.jp/2024/10/16/rimono_letter202410/
「スキルマップ」とは、端的に云えば、社員が業務を遂行する上で求められる力量(以下、「スキル」と呼びます。)を定義し、在籍社員の持つスキルを格付けして対照表の形式でまとめた一覧表です。「スキルマップ」の作成によって働き手の合理的な配置、計画的な育成、採用基準の明確化を目指す取組みにつながります。
厚生労働省では2002年度より「職業能力評価基準」の整備を進めており、事務系職種のほか製造業からサービス業まで、幅広い業種を対象としたスキルが公開されています。関連サイトに掲載されている「職業能力評価シート」をひな型として活用すれば、自社の事業や組織に適した「スキルマップ」を作成することができます。
厚生労働省「職業能力評価基準」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html
【お伝えしたい内容】
1. スキルマップの作成
「スキルマップ」の作成は、部門単位の業務を分解した後にそれぞれの業務に必要なスキルを抽出し、基礎能力、専門知識、技術・技能、社外資格などを階層別に定義する流れで行います。数十人規模であればExcelなどを用いることで作成できます。もしも社内リソースだけでの対応が難しい場合には、外部のシステム化されたツールを導入するのも一案です。
会社が複数の事業や部門を展開している場合、社内組織を横断するプロジェクトチームで取組むことになりますが、その際には要員配置、育成指針、採用基準などの重点方針を関係者間で明確に共有することが大切です。スキルを抜け漏れなく洗い出す必要があるものの、業務成果につながるスキルを実務に即した言葉で記述します。
また、部門単位で抽出したスキルに対してタイトルの付け方や格付け水準のルールを共有しておくことで、全社での比較や活用が可能になります。例えば「コミュニケーション能力」は多くの部門で共通のスキルと見なされますが、その定義が部門ごとに曖昧で異なっている場合、混乱が生じてしまいます。
次のステップでは、業務に必要なスキルに対して在籍社員がどのスキルをどの水準で保有しているかを、各部門長が格付け評価します。この評価にあたっては、専門資格の有無や潜在能力だけでなく、実際の業務成果につながった実務能力を重視することがポイントです。
一度作成した「スキルマップ」であっても事業環境や業務プロセスの変化に応じて定期的に見直す必要がありますし、格付け評価についても、社員の成長により変化することがあれば、逆に以前よりもスキルが発揮されなくなることもあります。そのため、人事考課と同じサイクルでスキルマップを更新することが望ましいと言えます。
2. スキルマップの活用
「スキルマップ」によって社員のスキルを把握できるようになれば、その内容に基づいて合理的な人員配置・人材活用が可能になります。社員が何となく適材適所に収まっているという状態から抜け出し、「スキルマップ」によって可視化された強みや課題を踏まえた人事異動や人材育成を計画することが求められます。
一方で、雇用の流動化が進み、働き手が個々のキャリアプランに沿って仕事を選ぶ傾向が強まる中、転職や退職はもはや珍しいことではありません。加えて、育児や介護による休業、病気療養のための休職などにより働き手が長期間離れることになる可能性もあり、不足したスキルへの対応に迫られるリスクは常に存在しています。
この意味において「スキルマップ」を活用し計画的に組織全体のスキル向上へ向けて取り組むことも大切です。例えば、日常業務の中での育成を工夫する、必要なスキルを保有する人材を求めて採用基準を設計する、中途採用者のオンボーディングを円滑に進めるなど、「スキルマップ」を基盤とした人事施策が考えられます。
また、「スキルマップ」からあらかじめ格付け評価の部分を除いて社内で公開すれば、会社が社員にどのようなスキルを期待しているのかを明示することができます。社員間の過度な競争をあおるような活用は望まれませんが、とくに若手社員に対しては仕事を通じて成長できる道程を示したいものです。
「スキルマップ」の作成には、一定の労力と時間を要し、意図した機能を発揮できるようになるまで試行錯誤を伴うかもしれません。しかし「スキルマップ」を軸として、上司はどのような育成指導を行い、部下はどのような行動を実践するべきかを管理職と部下がそれぞれの認識を共有することができます。
3. 研修受講・資格取得
「スキルマップ」を作成すると、業務から離れた教育研修や資格取得で習得する専門的なスキルよりも、実務経験を通じて身につける基本的なスキルが大部分を占めることがわかります。しかしながら、将来の基幹職となる働き手を確保するためには、若年層の社員に早期から専門分野のスキルを身に付けさせ、事業環境の変化へ適応できる基盤を築いていくことも重要です。
厚生労働省「人材開発支援策のご案内」令和6年9月1日改訂版
https://www.mhlw.go.jp/content/001084235.pdf
普段はあまり意識されませんが、就業規則に「会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、社員に対し、必要な教育訓練を行う」、「労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない」と定められていることが思い出されます。
専門分野のスキル習得のために会社が社員に研修受講や資格取得を命じる場合、その業務命令の法的根拠は、使用者が労働者の労働義務を遂行させるために有する指揮命令権(労務指揮権)に基づくと考えられます。職務に関連した必要な研修や資格取得であれば、社員は業務命令としてこれに従う義務があります。
一方で、業務命令による研修や資格取得に関わる費用は、会社が負担すべき経費です。仮に資格試験に不合格となっても、その費用を労働契約の不完全履行を理由に社員に自己負担させることは、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に反する恐れがあるため注意が必要です。
資格保有は、中途採用の応募者が持つ専門スキルを客観的に示す手段となりますが、当該分野で高いスキルを持つ社員がスキルマップに即して応募者の習熟度を裏付け評価すべき場合もあります。また、社外の資格制度では評価できない特定の技術や技能については、「スキルマップ」と連携させて社内独自の資格制度を立ち上げることも必要です。