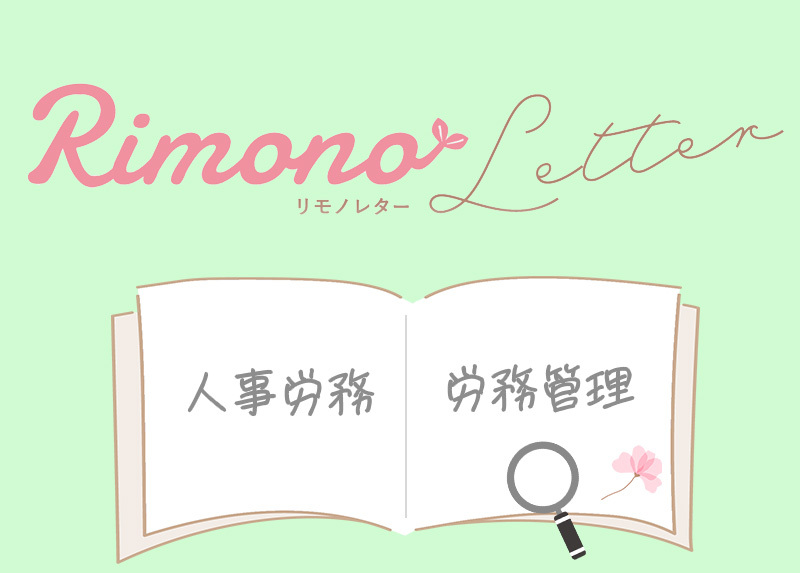従業員にメンタルヘルス不調が疑われる場合には、まず業務上の因果関係を確認することが大切です。長時間労働や不規則な勤務による過重労働が続いていなかったか、新しい職務を担当することになり圧迫された心理状態になかったか、あるいは職場で何らかのハラスメントを受けていなかったかなど……。そのうえで業務軽減、配置転換、休職発令などの適切な措置を実施しなければなりません。
メンタルヘルス不調(以下、「メンタル不調」といいます。)は、「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」と定義されています(厚生労働省・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」)。
労災認定基準では、強いストレスにさらされて生じる心身の異常や困難を「精神障害」と分類していますが、直近の労働安全衛生調査では、1か月以上の連続休業者や退職者が発生した事業所の割合が13.5%となっているほか、精神障害に関する労災請求・認定件数は毎年増加し、過去最高を更新しています。
厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」 令和7年6月25日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html
他方で、個人の健康情報は慎重に取り扱うべきものであり、とりわけメンタル不調についてはプライバシーに対する十分な配慮が求められます。会社が従業員のメンタル不調に気付いた際には、安全配慮義務(労働契約法5条)に則して必要な措置を検討しつつ、深刻な事態を防ぐために産業医や専門医の受診へとつなげる対応が不可欠です。
採用活動にあたっては、入社後に避けがたいストレス要因(例:顧客対応など)を予め説明することや、適性検査の実施によって本人の行動特性を確認し、メンタル不調のリスクを把握しておくことも、安全配慮の第一歩といえます。なお、本年5月に成立した改正労働安全衛生法では、50人未満の事業所においてもストレスチェックの実施が義務付けられることとなりました(2028年までに施行予定)。
【お伝えしたい内容】
1. 早期発見
個人によってメンタル不調の現れ方はさまざまです。本人が頭痛・めまい・疲労感などの体調不良を自覚する場合もあれば、申し出がなくても周囲が言動の違和感に気付く、注意力や集中力の低下により単純な仕事のミスが増えるということもあります。こうした異変を察知する周囲からの声掛けが、メンタル不調を把握する起点となります。
本人が体調不良を自覚していても、職場への申告によって自身の評価が下がり不利益を被る可能性を恐れ、無理をして働き続けることがあります。しかし、不調を放置すると仕事への意欲が低下し、遅刻・欠勤の増加、言動の不安定さ、身だしなみに構わなくなるなど、心身のバランスの乱れが周囲にも明らかになっていきます。
こうした場合、職場の上長や同僚が「何か困っていることはないか」と声を掛け、一時的な不調であれば有給休暇を薦めて休養させる、業務が原因であれば業務軽減などの対応を図ることが大切です。本人が受け入れず症状の悪化が懸念される場合には、会社の安全配慮義務にもとづき産業医や専門医の診察につなげる必要があります。
メンタル不調を放置すれば、勤務継続が難しくなり無断欠勤の後に会社との連絡を断つケースもあります。大事なことは、本人を責めるのではなく「あなたのことを心配している」という気持ちを使えることです。周囲が異変を感じていることを伝えつつ、「病気ではないかどうか、医師に確認してみては」と促すことが有効でしょう。
会社に産業医がいない場合、まず身近な医療機関の受診を勧めます。過去にかかりつけだった内科医であっても、メンタル不調が疑われる場合には専門医を紹介するはずです。ただし、専門医は予約が取りにくいことも多いため、その待機期間には残業制限や短時間勤務など、慎重かつ柔軟な対応が求められます。
2. 診断書の読み方
上記のような経緯でメンタル不調者が専門医の診察を受けた後、会社は本人に診断書の提出を求めます。診断書は、心身の不調を医学的に証明する重要な書類です。会社は安全配慮義務を負う立場として、その内容にもとづき、病状の悪化を防ぐための適切な対応や措置を検討・実施しなければなりません。
提出された診断書には病名や症状のほか、就労の可否、残業・出張などの制限措置、その必要期間が記載されています。ただし、発症の背景に入社前からの持病があるのか、過去の不調による服薬歴があるのか、あるいは担当業務や職場環境などのストレスが要因となっているのかといった点は、診断書からは読み取れません。
また、仕事を休みたくないとの思いから本人が医師に十分な説明を行わず、結果的に「就労可能」の診断が出される場合もあります。会社がその内容に疑問を抱く場合には、本人の同意を得たうえで、医師との面談に会社担当者が同席し、直接意見を伺う方法を選択することもあります。
一方、医師から「就労不能」の診断が提出された場合には、当面は自宅療養を指示し休職の発令を検討します。休職は本人の申し出によるものではなく、就業規則にもとづき会社が一定期間の療養に専念させる措置です。その際には、休職期間、定期報告の方法、休職中の給与や社会保険料の取り扱い、復職の手続き、復職できない場合の対応などを書面で通知します。
休職期間中の定期報告を受けることによって、本人の体調が回復に向かっているのか、依然として療養を要するのかを確認し、その記録を残しておきます。メンタル不調による就労不能の診断は長期化しやすい傾向にあり、休職期間を延長せざるを得ない場合も少なくありません。
*休職から復職までの対応については次号でご案内いたします。
3. 業務起因性
メンタル不調が見受けられる従業員については、直近で過重な長時間労働が続いていなかったかなど、本人のストレス状況とメンタル不調との因果関係(以下、「業務起因性」と言います。)を調査する必要があります。仮に本人からの申告がなくても、会社の責任が問われる対象の事案であるかどうか、リスク評価を行うことが重要です。
従業員から業務起因性を主張され労災保険給付請求の事業主証明を求められる、あるいは労災認定を経て損害賠償請求を受ける場合もあります。業務起因性を争うときは、事業主証明をあえて拒否する、または使用者意見を別途書面で提出することも認められています。将来的な損害賠償請求の可能性も踏まえ、記録の整備を含めた慎重な対応が必要です。
2023年9月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正・施行され、企業の安全配慮義務に関連し、精神障害を発生させない職場環境の整備等が求められるようになりました。この改正にあたり、ハラスメント行為として「顧客・取引先・施設利用者等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)」が明確に位置付けられることになりました。
厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要」令和5年9月1日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf
会社がメンタル不調を予防するためには、長時間労働や不規則な過重労働を防ぐ、ストレスチェックを実施する、高ストレスの従業員に対する面接指導を行うなど、すでに周知されている取り組みが基本になります。また、配置転換や昇格・昇進など仕事内容が大幅に変化する場面では、心理的負荷に配慮した指導・研修を実施する対応も挙げられます。
もっとも、従業員のメンタル不調を確認できないにも関わらず不合理な対応で休職させた場合には、その違法性を争われる可能性があります。例えば、「精神的に弱く、業務遂行に必要なコミュニケーション能力を欠いている」など、就業規則に定められていない事由を後付けして休職を発令することは避けるべきです。