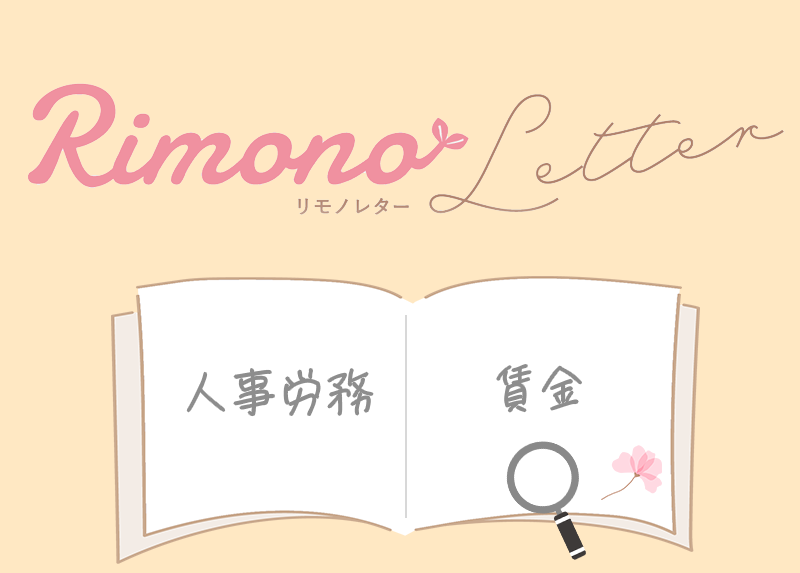2023年以降の物価上昇を背景とする賃上げの流れに対応するため、これまでのRIMONO Letterでは、自社の賃金水準が競合他社と比較して劣っていないかを把握し、諸手当の見直しや業績連動型賞与の導入などについてご案内してきました。本号では、引き続き「自社に明確な賃金制度が整備されていない」という前提に立ちつつ、限られた賃上げ原資の中でどのような対応策が可能かを考えていきます。
RIMONO Letter 過去の掲載テーマ
「制度未満の賃上げについて」後編 (2023.02.02)
「雇用の出入口での賃金設定について」 (2023.04.03)
「リテンションについて」 (2024.02.05)
「賃上げと諸手当の弾力性」 (2024.03.11)
「賃上げの流れは続く」 (2024.08.22)
現実問題として、近年の物価上昇による従業員および家族の生活コストの増大は、職場環境の良さ・仕事のやりがい・個人の成長意欲などの価値的要素では吸収しきれないレベルに達しています。また、働き手不足を商機とする転職サービス会社の積極的な営業活動が続いていることから、とくに若年層の従業員は、転職による賃金増加の可能性を常に意識させられている状況です。
総務省統計局 2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)2月分(2025年3月21日公表)
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
このような状況の下で、会社は優秀な人材を引き寄せ、仕事への意欲を高め、適切な処遇を維持するために一段と努力しなければならなくなっています。今年の春闘では、大手企業が高水準の賃上げを発表しました。成長分野で貢献度の高い人材を優遇する、新卒・中途採用を問わず優秀人材の賃金水準を重視するなど、どの職層・職域を対象に、どの程度、どの賃金要素で賃上げを実施するかという社内調整が行われたであろうことが推察されます。
もはや中小企業においても、ベースアップ(基本給の引き上げ)の実施はやむを得ないかもしれません。とはいえ、可能なかぎりの価格転嫁やDX化による生産性向上に取り組んだとしても、賃上げのための充分な原資を確保するまでには時間がかかります。さらに人材の引き止め(リテンション)を重視する場合には、想定外の賃上げに踏み込まなければならないケースも起こり得るのではないでしょうか。
今後も企業規模を問わず、賃上げの流れは続くと見込まれます。そこで以下では、賃上げの検討にあたって中小企業の組織課題と擦り合わせつつ取り組める方法についてご紹介していきます。
【お伝えしたい内容】
1. 調整手当
基本的には、全社一律のベースアップに加えて適切な昇格・昇給を実施できることが理想ですが、賃上げの原資に制約がある場合には、対象となる職層や職域を分けて優先順位を付けることが合理的な方法です。また、働き手不足の状況では、新卒だけでなく中途採用においてもそこそこの平均的な賃金水準で優秀な人材を引き寄せることは困難でしょう。
一方で、新卒・中途採用の賃金水準を引き上げれば、在籍者の関心を呼ぶことは避けられず、自社の賃金制度が整備されていない場合であっても、社内の賃金バランスを維持するための措置が求められることになります。こうした場合は、対象者を絞り込んだ賃上げを行うことで、主力となる基幹職層の優秀な人材に対して賃金水準を補正するのが有効です。
同じ目的で導入される手当には、資質能力の評価による調整手当、成績評価による賞与増額、目標達成による成果手当などがありますが、とりわけ安定して支給される月例の調整手当は、基幹職層の優秀者と信頼関係を結びつつ、リテンション効果を期待できるのではないでしょうか。ただし、調整手当は恒久的に支給されるものではなく、管理職層への昇格等により基本給の水準が上がるまでの期間限定措置である点を明確にする必要があります。
また、中途採用においては、前職の賃金水準を引き継ぐために調整手当を支給する慣行が一部で続いていますが、こうした補完的な調整手当は社内での受け止め方が曖昧であり、評価の公平性に欠ける側面を持っています。さらに、手当支給が恒常化してしまう可能性も否定できません。人材の市場価値に即した基本給を支給し、調整手当に頼った対応はできる限り避けたいところです。
2. クロス・トレーニング
従業員全体を職層や職域で区別してみると、一般職層で製造・販売・サービスなどの現場業務を支える従業員は、最低賃金に近い水準の賃金で就業している状況が続いているはずです。
さらに、パートタイム従業員については最低賃金改定の場合を除いて賃上げの実施対象から外されていることが多く、敢えて勤務成績に応じて数十円程度の昇給を実施しても、生計圧迫の実質的な緩和や仕事に対する意欲向上を期待することは難しいのではないでしょうか。最低賃金に近い水準の職層・職域では賃上げが充分に機能しないとも言えます。
パートタイム従業員のうち、2015年から2021年の間で最低賃金の時給+20円以内で働く人の割合が増加しているとの統計調査があります。大きな流れとして、今後の最低賃金の改定と人手不足の状況がどのような影響を及ぼしていくのか、次回以降の調査分析が注目されています。
厚生労働省 最低賃金近傍の労働者割合(賃金構造基本統計調査)
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/23/backdata/02-03-26.html
この課題に対して、新しいアイディアではありませんが、クロス・トレーニング(従業員が複数の業務や役割をこなせるようにする教育訓練)によって、業務全体の生産性を向上させる取り組みが考えられます。分かりやすく飲食店を例にとれば、ピーク時に接客を担当する従業員がドリンクを作る、または調理を担当する従業員が接客を行うなどのトレーニングです。担当業務の柔軟性を高めることでシフト人数を削減し、人件費総額を圧縮して一人当たりの賃上げを実現しようとするものです。
雇用契約書で定めた担当業務を変更する、新しい仕事を覚えるための教育訓練時間を確保する、などの工夫が必要ですが、一部では「年収の壁」を意識したパートタイム従業員が抵抗し、時給が上がるのであれば就業時間を減らすといった動きが発生するかもしれません。それでも従業員が自主性を持って協力し現場が回りやすく、多様な業務を通じて個々のキャリアアップにつながる機会も生まれます。
3. 分社化
賃上げの継続と組織課題の解消を組み合わせて取り組む際、一般職層や基幹職層に在籍する比較的勤続年数が長い従業員に対して、どの程度、どのように賃上げをするかについては、賃上げ原資の制約がある中で必ずしも優先順位を上げられない場合があります。しかしながら、古参の従業員は目立つ存在ではなくとも、一定の分野で安定した仕事ぶりを発揮している場合が多いかもしれません。
こうした貢献度が高い従業員を適切に処遇するためには、定型業務や専門業務を担当する部署を切り出して子会社を設立し、転籍出向を行う方法があります。子会社の設立といっても、独立した事業所としての体裁を整える必要はなく、同じ職場環境で本社との業務委託契約のもとで従来の業務を続けさせることができます。
古参の従業員には年功賃金の要素が反映され基本給を引き上げられてきた経緯がある場合でも、子会社の賃金水準を本社と別建てにすることで、賃上げにあたり本社の一般職や基幹職層とのバランスを考慮する必要がなくなります。彼らにとっては、雇用維持が確保され同じ仕事を続けられることが第一で、敢えて処遇改善を求めて転職に動き出す可能性は低いため、子会社への転籍を受け入れられるのではないでしょうか。
また、管理職層についても、一定のポジションに長く滞留する従業員を子会社へ転籍出向させたうえで上位の管理職へ昇格させる、あるいは役員として登用する方法があります。賃上げの対象からは外しつつも、独自の業績連動型賞与を導入することで仕事への意欲を保つことができると考えます。
【再掲】インフレ手当または第三の賃上げ 「リテンションについて」 2024.02.05より
急激な物価上昇に対する家計支援にあたっては、賃金の生活給的な要素と多様化したライフスタイルによる家計との間に、境界線を引くことがむずかしくなっています。
こうした状況のなかで、言わば現物支給の福利厚生制度として、会社が従業員のランチタイムに食事補助を提供する方法があります。時間、場所や提供メニューの限られた社員食堂や提携飲食店ではなく、就業場所近くにある全国展開のコンビニや飲食チェーンで利用できる電子マネーを配付するサービスです。
チケットレストラン
https://edenred.jp/ticketrestaurant/
会社の食事補助によって従業員が食べたいものを選べるという、わかりやすく、毎日メリットが実感できる手当であり、在宅勤務あるいは深夜勤務でも公平に使えます。電子マネーの配付が給与所得にならないよう非課税枠での補助額上限を設定することも可能で、飲食(酒、タバコを含まず)に用途を限定するため、換金性はありません。
地味なリテンションですが、従業員の家計支援を図る施策として理解・共感を得られるのではないでしょうか。